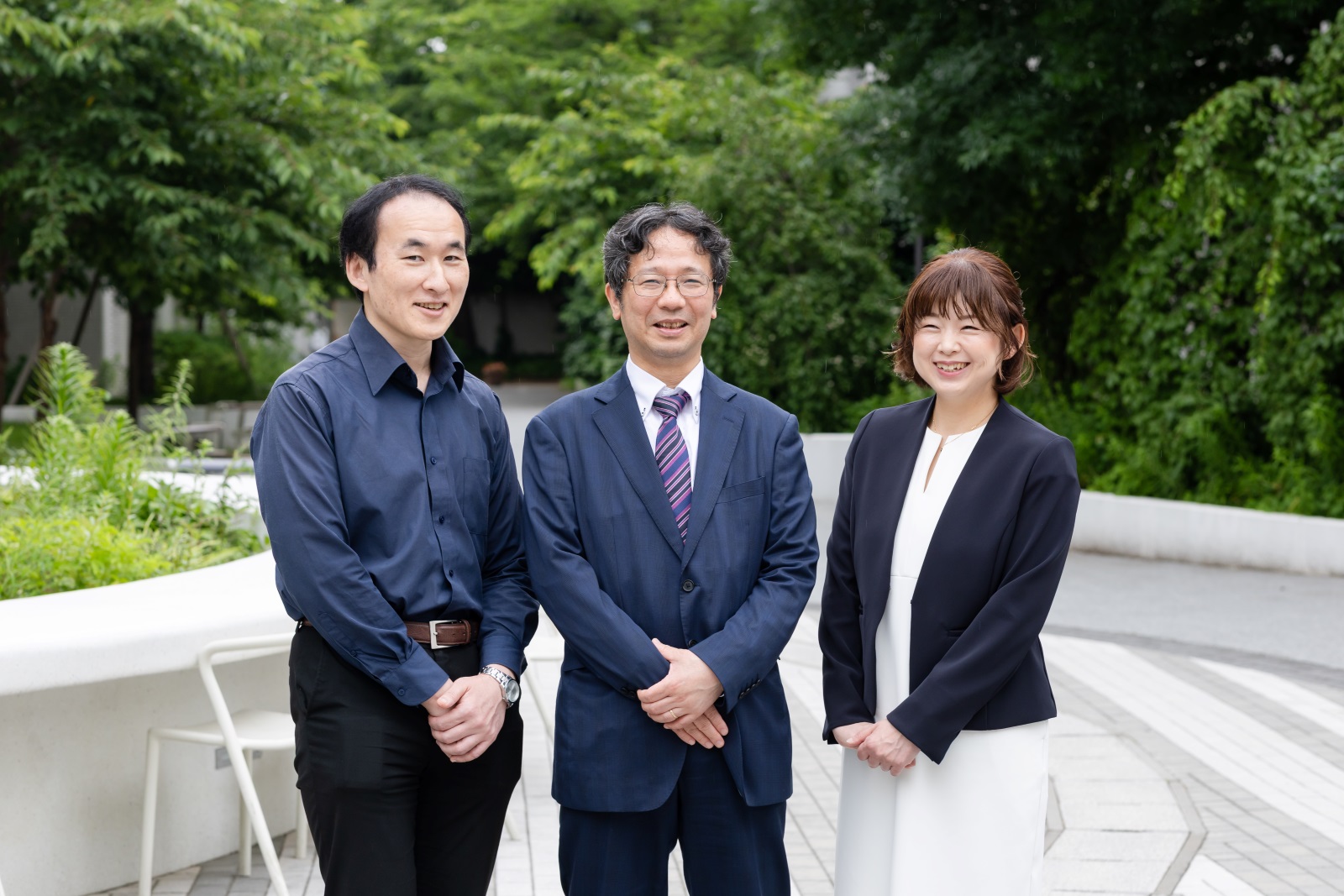■連載:大学職員座談会
売り手市場と言われ、年々、早期化している就職活動ですが、売り手市場だからと言って問題がないわけではないようです。学生たちの実際の就活はどのようになっているのか、キャリア支援担当の大学職員たちは何を感じているのか、都留文科大学、龍谷大学、創価大学の担当者に聞きました。(聞き手=朝日新聞「Thinkキャンパス」平岡妙子編集長、写真=Getty Images)
企業が求めるのは「人間力」
——企業側はどんな学生を求めているのでしょうか。
都留文科大学:本学は文系学科しかないものの、IT企業などからもよくお声がけいただくのですが、その際に企業側からよく聞くのは、「専門知識は問わないので論理的にものが考えられる学生や、人間的成長をしている学生、いわゆる社会人基礎力を身につけている学生にぜひ来てもらいたい」という話です。
龍谷大学:理系の場合はある程度、アカデミックな学力も重視されますが、全体で見るとやはり人間力が注目されています。それなのに、就職が早期化して1、2年生から就活に動いて学問そっちのけという面があるので、企業も頭を悩まされているのかなと思います。企業の方から「学生が薄っぺらくなっている」という話も聞きます。こんなこと言ったら怒られるかもしれませんが、1、2年生の夏休みはインターンシップよりも、一人旅に行くとか、ボランティアをするとか、そういう経験をしてほしいんですけどね。
創価大学:今の学生は社会課題と向き合っていく志の高さはかなりあるんです。だから、「実際に行動して実績を残したなど、自分にしかない経験を持っている学生はすごく光る」という話も聞きますね。
龍谷大学:人間性を高めるための本物の経験ですよね。インターンシップに行くのももちろんいいですが、それは3年生からでもいいのではないでしょうか。でも、1、2年生からやっとかなあかんというような逼迫感が学生たちにはあります。企業からは「真面目な学生が多い」という話をよく聞きます。「御社は第2志望です」と面接で言ってしまうとか(笑)。嘘も方便じゃないですが、その辺りもやはり人間力の要素であって、もう少しちゃんと揉まれなあかんのちゃうかなというところですよね。
「公平性」を求める学生
——学生の動き方にはどんな傾向がありますか。
創価大学:今の学生は「挑戦できる環境」と「安定性」の両方を手にしたいと思っていると感じます。そこに最近加わってきたのが、自分の仕事や成果がきちんと公平に評価されるかという「公平性」です。そのため、人事制度や評価の仕方をオープンにしている企業が学生たちの高い関心を集めています。
龍谷大学:企業からも聞く話ですが、転職を前提に就活している学生も増えているようです。学生にとって、その会社でどれだけのスキルを得られるかが重要な指標になっているというんですね。メディアがこれだけ転職を気軽なイメージで広めてしまうと、学生も転職ってすぐできるんだと勘違いしてしまいます。さらに、嫌だったらやめたらいいや、と考えてしまうんです。現実はそんな簡単なものじゃありませんが。
都留文科大学:面談中に「転職前提で考えることって、ありですかね」と素直に聞いてくる学生もいるので、「現時点から転職ありきで考えるのは絶対やめたほうがいいよ」とアドバイスしていますけどね。
エージェントが介入し、自分で決めない
——学生の意識もかなり変わってきているのですね。
龍谷大学:就活にかなりエージェントが入ってくるようになったので、その影響も大きいでしょうね。何もしなくてもエージェント側からどんどん声がかかるから、言われるがままにやってしまう。そうやって「汗をかかない就活」が主流になってきているのは怖いなと思います。転職の話も含め、学生にとって内定の重みが変わってきているなと感じます。
都留文科大学:そういう学生が増えてきていますね。本人が意図しないところでエージェントに登録され、困ってしまったなどという話も聞きます。
創価大学:ここ数年、エージェントの進出度合いは本当にすごいです。現在は若い労働力が不足しているので、割と簡単に内定が取れるようになっています。そんな中でエージェントは何を提供しているのかというと、結局、学生が自分の人生について考える時間を肩代わりするサービスだと思います。何が自分に向いているのか、本当にやりたいことなのか、もがいてほしいと思っています。大学は本来、自分の人生を自分で決めていく力を身につける場なのに、そこがアウトソーシングされています。大事な人生の意思決定を他者に委ねていいのかと、かなり疑問に思ってしまいますね。 自分で決めることを、手放さないでもらいたいです。
——就職活動にそんなにエージェントが入ってきているというのは驚きです。
都留文科大学:最近も学生から、「エージェントの適性検査を受けて、自分に向いていると紹介された企業4〜5社にエントリーしてみたけれど、何かしっくりこない。どうしたらいいでしょう」という相談を受けました。
創価大学:エージェントもいろいろあって一概には言えませんが、どうしても資本の論理が働くので、手数料が高い企業にあっせんしやすくなるという面がありますよね。教育機関としては、抵抗すべきところは抵抗して、学生本位を願いますが。
都留文科大学:やはり成功報酬みたいなビジネスモデルが多分にあると思うので、そこはケアが必要だと思います。
龍谷大学:キャリア採用ならエージェントもありかなとは思います。専門性や経験で見る部分が大きいですし。でも、新卒の真っ白な学生に対してエージェントってどうなんだろう。それこそ成功報酬の影しか見えてこないですよね。
創価大学:気持ちが優しい学生ほど、エージェントに引っ張られて断れなくなってしまうケースがあります。企業側に目を向けても、学生が長く働いている企業はやはり採用を大事にしているので、基本的に自前で採用活動をしています。一方、エージェントに丸投げの企業は短期的に人が欲しいだけということも多いんです。実際、エージェントに紹介された会社で長く頑張っているという話はあまり聞きません。学生にとってもそうした経緯で入社してしまうと納得度も低いので、大変な時に踏ん張れる原動力がないのかなと思います。やはり、学生にとってあまり幸せな結果にならないのではないかなと思いますね。
>>大学生の就職活動、担当者のホンネは「サポートしすぎかな?」 大学職員の本音座談会【前編】
>>子どもの就活を心配しすぎる、氷河期世代の親たち 世代間ギャップも影響か 大学職員の本音座談会【後編】
(文=小元佳津江)
あわせて読む
記事のご感想
記事を気に入った方は
「いいね!」をお願いします
今後の記事の品質アップのため、人気のテーマを集計しています。
関連記事
注目コンテンツ
-
「人間性重視」の教育で、AIにも負けない作業療法士を養成――文京学院大学・作業療法学科
一人ひとりの個性に合わせてリハビリテーションを行う作業療法士。対象者に寄り添い、懇切丁寧な応対が求められる作業療法士...
2025/07/18
PR
-
甲南女子大学はなぜ就職に強いのか?~大学全体で取り組む「誰一人取り残さない手厚い就職サポート」の実践
兵庫県神戸市の中心部近く、海と街並みを見渡す高台に佇む甲南女子大学は、手厚いキャリア支援と高い就職実績で、近年注目を...
2025/07/18
PR
-
社会が求める女性のデジタル人材を育成―― 昭和女子大学が初の理工系学部「総合情報学部(※1)」を2026年4月開設予定
大学通信が調査した「2024年 進路指導教諭が評価する大学」で、実に6項目にわたって「全国の女子大学1位」を獲得した...
2025/07/15
PR
お悩み
-
東京理科大学へ入学を決めた理由、高校時代・受験の思い出、キャンパスのお気に入りスポット、将来の希望進路・目標など学生...
2024/05/15
-
成績次第で没収?時間制限? 受験生と親、「スマホ」バトルを避けるには
■大学進学お悩みなんでも相談室 受験を控えた子どもを抱える保護者にとって、大きな悩みのひとつが「スマホを好き放題に使...
2023/06/30
-
合格するための睡眠とは? 入試直前、夜型から体内時計を調整する方法
■特集:大学入試を乗り越える 受験生は「寝る間を惜しんで夜中まで勉強」という生活になりがちですが、本番でしっかりと頭...
2025/01/09
キャリア(就職)
-
授業で深まった自己分析 納得いくまで就活続けて勝ち取った希望の会社
■私の就活体験記 大学を選ぶ際、ぜひ確認しておきたいのが、大学の就活サポートです。3年からの就活期間のみならず、入学...
2023/12/17
-
IT大手・富士通社員の就活体験記 インターンシップや説明会は50社以上 企業の「パーパス」が重要
■私の就活体験記 大学でのキャリア教育が重視されるなか、卒業後の進路に注目が集まっています。新卒で就職した先輩たちは...
2023/12/16
-
信州大学
人間の賢さをロボットに(信州大学 工学部機械システム工学科 教授 山﨑公俊)
ロボットの研究が人間の能力の解明につながる? 人間の賢さをロボットに取り入れることができれば、自動化やロボティクスが...
2023/06/27
-
-
読者モデルが多い大学ランキング!ベスト5を当てろ!やっぱり青学が1位?まさかの大学が…
お悩み募集メールはこちら↓ 【アドレス】 daigakudokoiku.staff@asahi-dl.com 進学に...
2023/06/26
-
-
京都産業大学
学生が起業を目指して新たな価値を創造! 「ビジネスプランコンテスト2024」開催!!
京都産業大学の交流・共創スペース【Innovation HUB】で、起業家を目指す 学生がビジネスアイデアを競う「ビ...
2025/07/02
おすすめ動画
大学発信の動画を紹介します。
大学一覧
NEWS
教育最新ニュース
- 広島「平和の灯」、愛知の高校生が名古屋へ自転車リレー 戦後80年 2025年 08月 04日
- 中高の受講生急増の東大メタバース工学部 学部長が高校行脚で手応え 2025年 08月 03日
- 日本で100年以上続く夏休みの宿題 「ゼロ」の欧米で起きる不平等 2025年 08月 02日
- 「子どもの良い成績にこだわらない」保護者が増加 国の学力調査 2025年 07月 31日
- デジタル環境で子どもの学力ダウン? 学力格差の専門家が挙げる要因 2025年 07月 31日
Powered by 朝日新聞