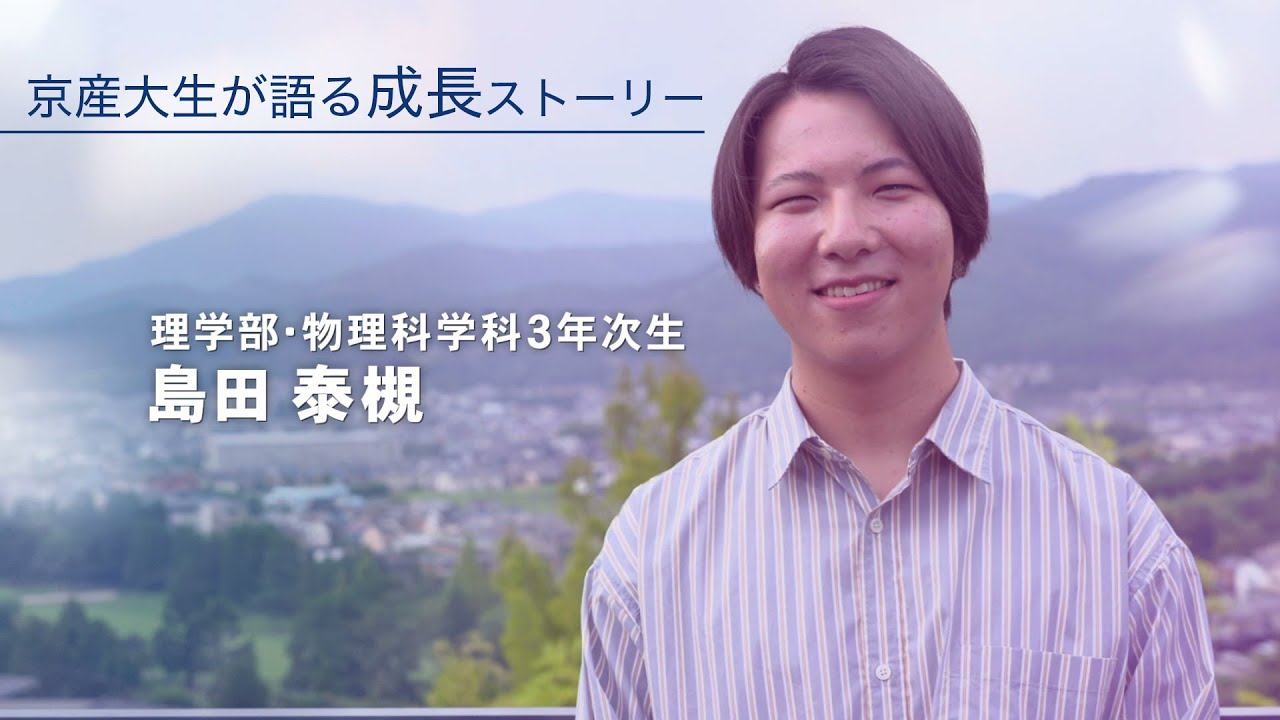■特集:保護者の悩み・スマホは受験の味方?
スマホの使いすぎは学力にも悪影響を及ぼす――。そんなドキッとするような調査結果があることを、ご存じでしょうか。脳機能研究の第一人者であり、スマホと学力との関係を追究している東北大学加齢医学研究所の川島隆太教授に、最新研究のデータから解説してもらいました。(写真=Getty Images)
スマホを使うほど下がっていく成績
「スマホを使いすぎると、せっかく勉強したことが台なしになってしまいます」
脳トレゲームの監修などでもおなじみの川島教授は、そう言い切ります。2010年から仙台市と協力して市内の小中学生の学習意欲に関する調査研究を続けていくなかで、偶然あることに気づきました。
まずは、下のグラフを見てください。「学力検査の成績」と「スマホ*1についてのアンケート回答」をもとに、小学5年生から中学3年生までの「成績」と「平日に勉強以外でスマホを使う時間」との関係をグラフにしたものです*2。成績(縦軸)は、スマホ使用が「1時間未満」の場合が最も高く、使用時間(横軸)が長くなるほど低くなっているのがわかります。
*1 アンケートではインターネット接続できる機器全般について聞いていますが、実際は大半がスマホのため「スマホ」としています。
*2 調査時点の仙台市の小中学生のスマホ保有率は、小学5、6年生が約6割、中学生が約7割です。

「スマホを全く使わない子どもよりも、1時間未満の子のほうが成績が良いというのは、自分の意思で使用時間を1時間未満にコントロールできている子が含まれる可能性があると考えています。そこを除けば、スマホを使うほど、学力への悪影響が出ていることがはっきりと読み取れます」(川島教授)
3時間以上の使用で平均点を取れた子はゼロ
なぜ、スマホを使うほど学力が下がるのでしょうか。
一般的には「勉強時間を確保できていない」「睡眠不足で集中力が下がっている」といった理由が思い浮かびますが、「そのどちらでもありません」と川島教授は断言します。それを裏付けるのが、先ほどの「成績×スマホの使用時間」のデータに「勉強時間」と「睡眠時間」も加え、「スマホの使用時間」ごとに見た次の3つのグラフです。



グラフは上から順に、スマホの使用が1時間未満、2~3時間、3時間以上の子どもたちの成績を表しています。棒の高さは成績を表し、色はグレーが平均点以上(偏差値50以上)、白色が平均点以下を意味しています。その色に注目するだけで驚くべきことが見えてきます。グラフが下に行くほどグレーの割合が減り、スマホの使用時間が3時間を超える3つ目のグラフに至っては、勉強時間や睡眠時間に関係なくグレーが一つもないのです。
それだけではありません。例えば、「睡眠7~8時間」という同じ条件下で成績を見比べてみましょう。すると、スマホを3時間以上使っている子は、勉強を3時間以上やっていたとしても平均点以下で(グラフ内・赤矢印)、30分未満しか勉強していないが、スマホは1時間未満という子(グラフ内・青矢印)にすら成績が及んでいないこともわかります。
成長期の脳が発達しない
川島教授は次のように語ります。
「平均11歳の子ども223人の脳を3年間モニタリングした結果、スマホを含むネット漬けの子どもほど、思考や創造のほか、人の気持ちを理解したり、場の空気を読んだりするような高次なコミュニケーションをつかさどる前頭前野を中心に、脳が発達していないことがわかりました。記憶や学習に関わる海馬や、言葉に関係する領域などにも影響が見られます。スマホを使っているときは脳があまり活発に動いていないという文献は多く出ていますが、スマホは人間が楽をするための道具ですから、当然といえば当然です。紹介した調査は小中学生を対象としたものですが、成長段階にあるという点では、高校生にも同じことが言えます。ついでにお伝えすると、すでに成長している大人も安心できません。使わない機能は、どんどん衰えていきます」
中高生は、コミュニケーションに関わる前頭前野が特に発達する時期ですが、スマホで楽をしてしまえば、その発達が打ち消されてしまう可能性があります。逆に、スマホの使用をコントロールできる人の脳は、勉強や日々のコミュニケーションなどによって活発に動くため、「気づいたときには大きな差が開いているのではないでしょうか」と川島教授は警鐘を鳴らします。

ただし、暗い話ばかりではありません。
「脳は、悪い習慣を断ち切るだけで、機能が回復することもわかっています。つまり、スマホと上手に付き合えるようになれば、再び発達していきます。実際に、2015年度から2年間にわたって、同じ子どもの小学6年時と中学1年時の成績とスマホの使用時間を調べた追跡調査では、スマホの使用時間を1時間未満に抑えることができた子どもは、成績も伸びていました」(川島教授)
とはいえ、子どもの日常生活にも入り込んでいるスマホの使用時間を減らすのは、簡単なことではなさそうです。どう付き合っていけばいいのでしょうか、後編に続きます。
>>後編 「受験期のスマホ制限、偏差値に影響」 脳トレ・川島教授が思う学力との関係

川島 隆太(かわしま・りゅうた)/東北大学加齢医学研究所教授。脳活動の仕組みを研究する「脳機能イメージング」のパイオニアであり、脳機能研究の第一人者として知られる。ニンテンドーDS用ソフト「脳トレ」シリーズの監修者でもある。主な著書に『スマホが学力を破壊する』(集英社)など。
(文=竹倉玲子)
記事のご感想
記事を気に入った方は
「いいね!」をお願いします
今後の記事の品質アップのため、人気のテーマを集計しています。
関連記事
注目コンテンツ
-
物質の境界「界面」の不思議と未来への可能性 — 千葉工業大学応用化学科
異なる性質を持つ二つの物質が触れ合う境界――界面。界面は物質の内部と異なる特有の性質を有し、さまざまな現象が生じる。...
2025/12/24
PR
-
むずかしい科学を正しく、やさしく伝える力を育む――来春、東京理科大学に科学コミュニケーション学科、開設!
多くの情報があふれるデジタル社会で、多様な立場の人に科学をどうやって伝え、議論し、社会課題を解決していくのか――。こ...
2025/12/22
PR
-
諏訪から世界へ! 公立諏訪東京理科大学が推進するグローバル教育と国際交流活動
長野県茅野市は、精密機械をはじめとするものづくり産業の集積地・諏訪地域の中部に位置する。人口は約5万5000人。この...
2025/12/19
PR
入試
-
【新課程・共通テスト】「情報I」どう対策? 配点なし・成績同点者の順位決定に使うケースも
■教育系YouTuber&専門家と予測する 2025年度大学入学共通テスト 2025年度の大学入学共通テストから、新...
2024/01/12
-
東京理科大学へ入学を決めた理由、高校時代・受験の思い出、キャンパスのお気に入りスポット、将来の希望進路・目標など学生...
2024/05/15
お悩み
-
将来は大学に行きたいと考えたとき、そのためにはいつから受験勉強を始めたらいいのか、という疑問が出てくるものです。この...
2025/07/03
-
「東大はやめたい」息子の志望校変更に、父「就職に不利になる」 親子戦争、どう解決した?
■先輩パパ・ママの受験体験記 志望校を巡って、父親と意見が合わずに衝突を繰り返す次男との間で、神奈川県の山中里江さ...
2023/11/02
おすすめ動画
大学発信の動画を紹介します。
大学一覧
NEWS
教育最新ニュース
- 国公立大入試の2次試験出願 文科省が中間集計を発表 2026年 01月 30日
- 女子中学生に売春させた疑い、少年6人逮捕 SNSで「仕事せん?」 2026年 01月 30日
- 短歌に向き合う時間が力に 定時制高元教員が最後の授業で伝えたこと 2026年 01月 29日
- 高校野球部監督が体罰で処分 練習でミス、連帯責任で腕立て300回 2026年 01月 29日
- 「生きたくないけど生きてる」子どもたち 大人が示せることは 2026年 01月 29日
Powered by 朝日新聞