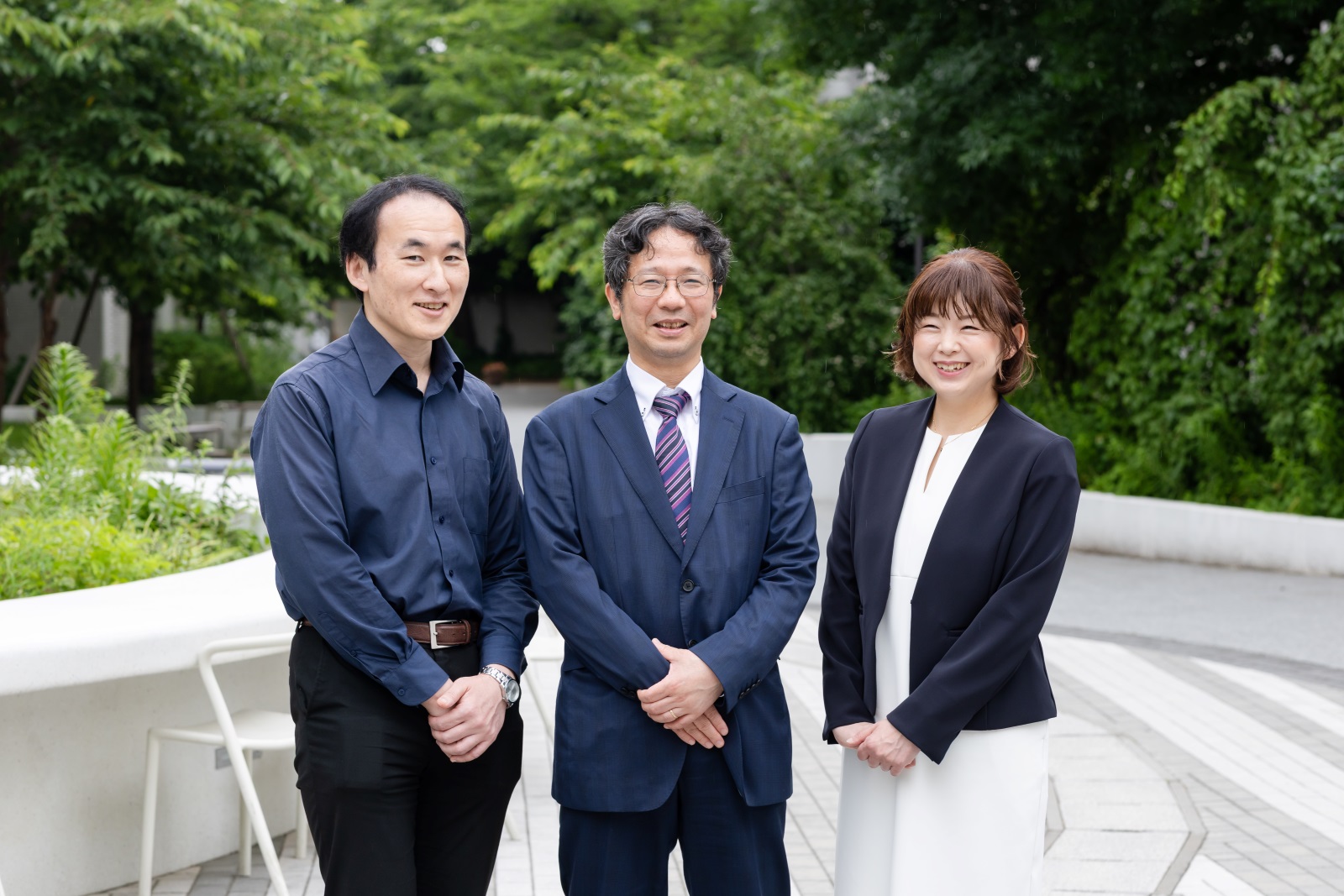■話題・トレンド
勉強した時間や教科を記録できる学習アプリ「Studyplus」の運営会社スタディプラスの代表取締役を務める廣瀬高志さんは、慶應義塾大学法学部在学中の2010年に会社を起こしました。「学ぶ喜びをすべての人へ」をミッションに掲げてサービスを展開する同社ですが、この発想には、廣瀬さん自身の受験・浪人の経験で得たことが生かされています。(聞き手=朝日新聞「Thinkキャンパス」平岡妙子編集長、写真=スタディプラス提供)
予備校で感じた「物足りなさ」
――「Studyplus」の主なユーザー層は中高生です。廣瀬さん自身、高校時代はどのように過ごしましたか。
東京大学に何人も合格するような、東京・国立市にある私立の進学校に通っていました。そこで私も東大を目指して勉強していたのですが、所属していたバスケットボール部の先輩の中に、その年の最高得点で東大に合格した人がいたんです。先輩に「どうしたらそこまで勉強に打ち込めるのか」と聞いたところ、「勉強記録ノートをつけるといいよ」と言われました。
そこで、どの教材で何時間勉強したかを記録するノートをつくり、学習時間をグラフ化するようにしたところ、計画的かつコンスタントに勉強ができるようになりました。科目の偏りも可視化でき、学習計画の振り返りもできて、記録することの重要性に気づくきっかけになりました。
――学習の記録をつけられる「Studyplus」の原点のような出来事ですね。
友達とはよく、「受験勉強で一番大事なのはモチベーションだよね」と話していました。勉強を教わったり、勉強したりすることはもちろん大事ですが、学習計画の立て方や勉強の仕方を教えてもらったり、意欲向上につながるコミュニケーションを取ったりすることも、勉強そのものと同じくらい大事だと感じていました。
高3の時には東大以外は受験せずに、浪人してしまいました。それで予備校に通ってみたら、当時は大教室で一斉授業を受けるだけ。それ以上のサポートなかったので驚きました。と同時に、受験生に対してもっといいサービスが提供できるのではないか、とも感じるようになりました。結局、一浪して慶應義塾大学に進学しましたが、当時の経験は、今の自分にとてもプラスになっていると思っています。
「自分がやらなければ」という使命感
――大学に入って、いつ頃から起業したいと思うようになったのですか。
大学では1、2年の頃から、ベンチャー企業でアルバイトなどを経験しました。4年になって「就活はどうしようかな」と考えていた時、学生向けのビジネスコンテストが開催されることを知り、出てみることにしたんです。「インターネットを使ったビジネスプランを考えよ」というのがテーマで、私が提案したのが「ITを活用した家庭教師会社」でした。スマートフォンで勉強の記録ができる、独自のソフトウェアが強みの会社です。この会社なら、家庭教師が生徒の家に行かない日でも学習管理ができ、ちょっとしたやり取りでモチベーションの維持もできるということをアピールしました。
――まさにご自身が受験した時に求めていたものを形にしたのですね。
コンテストでは、優秀賞をもらいました。我ながらびっくりの高評価でしたが、主催側の経営者の方にも褒めてもらったことで、「これはいけるんじゃないか。チャンスだ」と、大学生のうちに起業することにしました。

――起業したいという思いはもともとあったのでしょうか。
私の両親はともにリクルートに勤めていて、その社訓だった「自ら機会を創り出し、機会によって自らを変えよ」という言葉を、廣瀬家の家訓にもしていました。そんな家庭で育った私は、ゆくゆくは経営者になりたいと当然のように考えるようになりました。小学1年の時には、七夕の短冊に「将来は社長になる」と書いていましたからね(笑)。

――家訓に従った廣瀬さんを、ご両親も応援してくれたのではないでしょうか。
それが、最初はそうでもなかったですね(笑)。起業して1年後、仕事が忙しくなって大学中退を決めたのですが、「卒業はちゃんとしなさい」と、母には泣かれました。自分にも不安がなかったわけではありませんが、「これで絶対に成功できる」「自分がやらなければ」という使命感がありました。学習者にとって最大の課題は、勉強を継続することの難しさにあります。ここにフォーカスしたサービスは、世界的に見てもまだほとんどありません。だからこそ、自分がこのサービスを広めるんだという強い思いがありました。
学ぶ人のための課題解決を
――学習履歴を管理できるアプリ「Studyplus」は、現在は多くの利用者がいます。ここに至るまで、苦労はありましたか。
初めはなかなか利益が出ず、伸び悩んだ時期がありました。アプリの主なユーザーは大学受験を控えた高校生なので、「Studyplus」は基本的に利用者には課金せず、広告収入で利益を得ています。しかし、2012年にアプリをリリースした当初は利用者が少なかったので、広告もなかなか思うように増えませんでした。この頃は先が見えなくてつらかったですね。
ただ、15年になるとユーザー数が100万人を超え、その頃から広告もコンスタントに入るようになりました。また、前身となるアプリ「studylog」にはSNS機能がなく、Facebookやmixiなど、外部のSNSと連動できるようにしていましたが、ユーザーにはこれがあまりウケなかったんです。「このアプリの中にSNS機能がほしい」というユーザーの声が多く、そういった声に応えてアプリを進化させてきたという経緯もあります。いまは有料プランもあります。
――SNS機能が強く求められるということは、受験を控えたユーザーにとっては記録だけでなく、コミュニケーションも大切だということでしょうか。
そう思います。友達を作るとまではいかなくても、同じ目標に向かって頑張っている人たちとタイムラインでつながっていれば、一人ではないと思えるのでしょう。勉強はどうしても孤独なものですが、その寂しさを和らげ、学習の継続を促す効果もあると思います。
――今後の方針を教えてください。
本来、教育は学習者のためのものです。しかし、現在の教育は教育者のためのものになっている部分もあると思います。私たちは本質を忘れず、学習者を中心にした課題解決を目指していきたいと考えています。わが社の行動指針は「学び変化する」。学ぶ喜びを体験して自ら変化することは、きっと未来の希望につながるはずです。アプリなどのメインユーザーは受験生ですが、社会人も含めて、学ぶ人を幅広く支援するべく、新たなサービスを開発していきたいです。
>> 【後編をもっと読む】スマホで勉強管理のアプリは、ついSNSを見ちゃうのでは? 親は知らない、スマホとの上手な付き合い方
(文=鈴木絢子)
【写真】スタディプラス・廣瀬高志社長の慶應大時代の写真
あわせて読む
記事のご感想
記事を気に入った方は
「いいね!」をお願いします
今後の記事の品質アップのため、人気のテーマを集計しています。
関連記事
注目コンテンツ
-
「人間性重視」の教育で、AIにも負けない作業療法士を養成――文京学院大学・作業療法学科
一人ひとりの個性に合わせてリハビリテーションを行う作業療法士。対象者に寄り添い、懇切丁寧な応対が求められる作業療法士...
2025/07/18
PR
-
甲南女子大学はなぜ就職に強いのか?~大学全体で取り組む「誰一人取り残さない手厚い就職サポート」の実践
兵庫県神戸市の中心部近く、海と街並みを見渡す高台に佇む甲南女子大学は、手厚いキャリア支援と高い就職実績で、近年注目を...
2025/07/18
PR
-
社会が求める女性のデジタル人材を育成―― 昭和女子大学が初の理工系学部「総合情報学部(※1)」を2026年4月開設予定
大学通信が調査した「2024年 進路指導教諭が評価する大学」で、実に6項目にわたって「全国の女子大学1位」を獲得した...
2025/07/15
PR
お悩み
-
入試でケアレスミスを防ぐ5つの方法 受験生のメンタル専門の心療内科医に聞く
■医師が教える・受験直前メンタルケア 共通テストや一般選抜に向けて、この時期になると勉強のスイッチが入ります。ただ、...
2025/01/07
入試
-
年が近いきょうだいの受験、親のサポート方法 佐藤ママはどうしていたの?
■思春期子育てお悩み相談 年齢の近いきょうだいでも、性格が全く違うことがよくあります。そうした場合、大学受験が近づく...
2025/06/02
-
-
早稲田大学
現代の新たな早稲田の森を創る 早稲田キャンパスに新たな知の拠点「新9号館」が誕生!
「世界で輝くWASEDA」の実現を目指し、早稲田キャンパスの新たな知の拠点として「新9号館」の建設することとなりまし...
2024/03/19
-
桜美林大学でパイロット体験👨✈️ハッピーフライトteam&グッドラックteamが空に飛び立つ✈️
桜美林大学のHPはこちら! https://www.obirin.ac.jp/academics/aviation_...
2023/06/26
-
-
おすすめ動画
大学発信の動画を紹介します。
大学一覧
NEWS
教育最新ニュース
- 津波注意報、離島の子はどう行動したか 学校のない時期の自主的避難 2025年 08月 13日
- 最速1年で教員免許、大学院に課程新設へ 社会人→教員を増やす狙い 2025年 08月 10日
- 東京独自の「チャレンジクラス」1年 公立中に分教室、続く試行錯誤 2025年 08月 09日
- 日本国籍なのに外国籍とされた少年 サッカー協会が「帰化」書類要求 2025年 08月 09日
- 科学力ランキング13位、過去最低3年連続 資材高騰も研究費増えず 2025年 08月 08日
Powered by 朝日新聞